
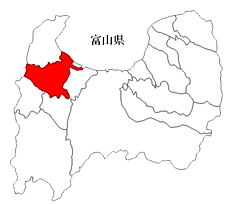
◎高岡市概要
高岡市は、富山県の北西部に位置し北は氷見市に接し、東は射水市、北西は石川県宝達志水町・石川県津幡町、南西は小矢部市、南は砺波市に接しています。
輝かしい歴史・文化資産に囲まれ、多様な産業・豊かな伝統を受け継ぐ活力とにぎわいあふれる都市です。
(高岡市HPより)


< 高岡大仏 >
高岡大仏は、奈良大仏・鎌倉大仏と並んで日本三大仏の一つに数えられ、その大きさは16mに及びます。
幾度も焼失・再建を繰り返し、昭和8年に現在のものが完成し、銅器の町高岡のシンボルとして親しまれています。

< 高岡地域地場産業センター >
高岡地域地場産業センターは、昭和58年に高岡西部地域の地場産業界と、県関係市町村によって、地場産業の振興と地域の発展を 目指すとともに広く県内外の方々に地域の産業を理解していただくために建てられたものです。

< 高岡御車山祭り >
高岡御車山は天正16年(1588年)豊臣秀吉が、後陽成天皇と正親町上皇を聚楽第に迎え奉る時に使用したもので、加賀藩初代藩主前田利家が秀吉より拝領し、二代目藩主前田利長が慶長14年(1609年)に高岡城を築くに当たり町民に与えられたのが始まりと伝えられています。
京都祗園の祭礼にならって鉾山に改造され、高岡関野神社の祭礼日に神輿と共に曳廻されて以来、今日にいたるまで高岡の発展と共に継承されてきました。御車山は御所車形式に鉾を立てた特殊なもので、高岡町民の心意気と財力に支えられ、格式を保ち高岡の金工、漆工、染織等の優れた工芸技術の装飾が車輪や高欄、長押等に施された日本でも屈指の華やかな山車です。 (高岡市HPより)

< 雨晴海岸 >
万葉集にも数多く詠まれた岩礁多く白砂青松の景勝地。日本の渚百選の一つにも選ばれています。
富山湾越しに望む立山連峰は世界でも屈指の絶景です。

< 国宝「瑞龍寺」>
高岡の開祖前田利長の菩提寺曹洞宗の名刹。3代藩主前田利常の建立で、壮大な伽藍配置様式の豪壮にして典雅な美しさに圧倒されます。
山門、仏殿、法堂が県内で初めて国宝の指定を受けました。 (高岡市HPより)

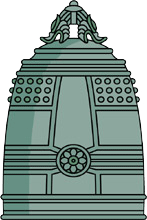
< 高岡銅器 >
高岡銅器は、江戸時代初期に加賀藩主・前田利長公が高岡築城に際し、河内丹南より7人の鋳物職人を招いて鋳物工場を開設したことに始まります。
高岡鋼器は花器、仏具等の鋳物に彫金を施す「唐金鋳物(からかねいもの)」を作り出したことにより発達、明治時代には、パリ万国博覧会に出品されるなど世界でもその存在が知られるようになり、全国の生産量の9割を占めています。
昭和50年には、日本で最初に国の伝統的工芸品産地の指定を受け、近年では大型ブロンズ像の製作に取り組み、有名作家のブロンズ像が全国での高岡銅器の知名度を高め、今日に至っております。
< 高岡漆器 >
高岡漆器は江戸時代初期、加賀藩の藩主前田利長が高岡城を築いたとき、武具や箪笥、膳等日常生活品を作らせたのが始まりです。
その後中国から堆朱(ついしゅ)、堆黒(ついこく)等の技法が伝えられ、彫刻塗、錆絵(さびえ)、螺鈿(らでん)、存星(ぞんせい)等多彩な技術が生み出されました。